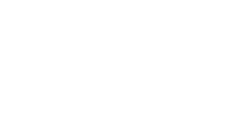記事
「(大学生活でやり残したことは)ないです」。そうきっぱりと答えたのは、副主将の小林亮太(総4=豊川)。
苦しい時期も糧にしてエース格に成長し、チームの要として躍動してきた。本記事ではそんな小林の、これまでの競技人生をたどる。

小林が陸上の世界に飛び込んだのは中学1年生の頃。当時は長距離が得意ではなかったというが、「仲の良かった友達がみんな陸上部に行ったので流れで始めました」。
流れで始めたこの競技で、自分の走る姿がテレビ放送される選手に成長するとは、この頃の小林は思っていなかっただろう。
だんだんと陸上競技にのめり込んでいった小林は高校時代に豊川高で全国高校駅伝を2度出走。着実に力をつけていき、大学でも競技を続けようと決意する。
大学進学の際、小林は東洋大を選んだ。その決め手となったのは「走ること以外にも、食事や生活全般を学べる環境」が整っていると感じたから。競技面だけでなく、人間としても成長できる場が広がっていると信じて東洋大への進学を決めた。
思い通りにはいかなかったルーキーイヤー
晴れて東洋大の門をたたいた小林。入学時の小林が目標としていたのは「1年生の頃から三大駅伝や関東インカレなどの主要大会で結果を出すこと」。しかし、1年目ではいずれの大会にも出場することはなかった。
「石田と梅崎が出走できたことに誇らしく思う部分もありましたが、同じ舞台に立てなかった悔しさもありました」。 思い描くようなルーキーイヤーとはならず、悔しい思いが強かった。しかし、「彼らと同じ舞台に立ちたい」。この思いが小林の陸上人生を大きく変えるきっかけにもなった。
陸上人生のターニングポイント
同期を追いかけて練習に励んできた小林にも、ついに殻を破る時が来る。それは2年時に出走した早稲田競技会。5000㍍を走り、13分台で自己ベストを更新した。「初めて自分の力を最大限まで出し切れた」。ここが陸上人生のターニングポイントだったと小林は振り返る。
「体作りを継続してきたことで、だんだんと上の選手たちと互角に走れるようになってきた」という小林は3年時に10000mで自己ベストを3度更新。全日本大学駅伝こそ苦戦したが、箱根駅伝では3区を任され、区間6位とエース格に急成長。最終学年では副主将に任命された。

3年時の箱根駅伝。主力としてタスキをつないだ
ラストイヤー、待ち受けていたのは試練
順調と思われていた競技生活。しかし、大学ラストイヤーで待ち構えていたのは"試練"だった。
「夏合宿頃から膝の方を痛めてしまって、そこからなかなか練習が積めなくて苦しい思いをしました」。
最後の三大駅伝を前に、自分を追い込みたいのにけがで追い込めない。そんな日々が続いてもどかしかった。それでも小林は逆境をはね返し、11月の全日本大学駅伝では1区で出走。復帰した姿を見せた。けがの状態は決していいわけではなかったが、その時のベストを出し尽くした。

全日本は1区での出走
最後の箱根駅伝、小林が果たした2つの役割
そして迎えた最後の箱根駅伝。小林は膝にテーピングを何重にも巻き、スタート地点に現れた。石田洸介(総4=東農大二)や梅崎蓮(総4=宇和島東)といったエース選手が不在の中、自身もコンディションが万全でない状態での起用だった。
監督やチームメートからの声かけは「緊張しすぎてあまり覚えていなかった」というほど。その中で2位集団の先頭とは13秒差に留めた力走を果たした。
小林が果たしたのは走者としての役割だけではなく、もうひとつの役割も全うしていた。
それは仲間を鼓舞する役割。小林は初の大舞台となる1年生に対して、「タスキをもらった時は心を落ち着かせて、余裕をもってスタートしてほしい」。そう声を掛けてプレッシャーを乗り越え支えようと努めていた。
「自分自身もすごく緊張をしていたのでチーム全体に声かけはできなかったのですが、1年生は初めての箱根駅伝ですし、緊張をしていたところもあったので個別に声かけをしました」。小林の気遣う心は1年生の力走にもつながった。

テーピングを巻きながらも、役割を果たした
振り返れば、この4年間は決して楽なものではなかった。「辛い時や楽しい時にいつも同期がそばにいてくれて、そのおかげで諦めずに4年間やってこれたので、同期には感謝しています」。苦しい時期も乗り越えて、小林がエース格にまで成長したこと。それは"同期の存在"があったからだと大学での競技生活を終えた今、小林は振り返る。
「(思い残したことは)ないです」。そうきっぱりと答えることができたのは、数々の困難を乗り越え、努力を結実させてきたからだろう。けがや不安を抱えながらもその時のベストを出し尽くし、チームを支え続けた姿。それはまさに東洋大学陸上競技部の精神そのものだった。
TEXT=北川未藍/PHOTO=東洋大学スポーツ新聞編集部