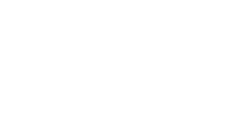記事
"激闘"の2文字がふさわしい。硬式野球部の秋季リーグ戦開幕カードの開催地の愛媛県松山市、全日本大学駅伝開催地の三重県伊勢市、全日本大学女子駅伝開催地の宮城県仙台市。様々な場所で鉄紺をまとう戦士たちを応援するために駆け付けた東洋大学応援指導部。そんな彼らにとって、激闘の1年となった2023の年の瀬に一大イベントが行われる。それは「鉄紺祭」だ。
2015年に第1回を開催以来、部員の減少や新型コロナウイルスの影響を受け、開催を見送った年やオンライン開催を余儀なくされた年があったりと様々な困難に見舞われてきた鉄紺祭。しかし、これらの困難を乗り越え、2023年12月3日、ついに有観客で帰ってくる。
今回は第5回鉄紺祭の開催を記念して、應援指導部第42代主将の秦芽吹さんにインタビュー。久しぶりの有観客となった鉄紺祭への意気込みや8月に行われた「鼎(かなえ)の舞」について聞いてみた。
※前回では応援指導部の活動について掲載しております。合わせてご覧ください。
[應援指導部] 選手と共に声で戦う!応援が力になる! 應援指導部の想い

――鉄紺祭を控えた今の心境はいかがですか
今回で第5回になりますが、近年ではすべてオンラインでの開催になっていたので、私たちとしても有観客での開催は初めてになります。なので、一番は緊張しています。
――久しぶりの対面開催になりますね
はい。今回は、第1回時より規模も大きくなっていて、応援指導部の演舞を初めて見るという方、OB・OGの方などたくさん来て下さる予定なのでとても楽しみです。
――今まで“誰かのために応援してきた”。今回は皆さんがメインとなり応援される側になりますね
今までは野球部や陸上部をメインで応援してきましたが、今回は来て下さる皆さんに元気を与えたい、そして40年以上繋いできたものを継承していることを見せる場だと思っています。東洋大学応援指導部の伝統を見ていただけると嬉しいです。

――ここまでどのような準備をされてきましたか
本年度からコロナによる規制が少なくなり、制限のない活動が私たちも初めてだったので会場であったり警備であったりと裏側の事を0から始めました。技術面では野球の試合や駅伝の大会を経験するたびに、下級生たちも応援自身を楽しんでくれてるような様子が見られて、応援に対する意識を部員全員で上げれたのかなって思います。みんなが応援を楽しめる、周りの人が見て元気になれるような応援が作れた半年間でした。
――メインで活動されてる野球応援ですが結果としては悔しい結果になってしまいました。しかし、チームが苦しいときに鼓舞し続け、様々なパフォーマンスを見せてくれました。応援指導部として1部で戦えた東都大学野球秋季リーグはいかがでしたか。
憧れの神宮球場で応援できたことは、私たちの経験としてすごく尊いものでした。球場で東洋側に座っていただいて、私たちの応援を見ていただいた。その方々から鉄紺祭に来たいという声もいくつかありましたので、私たちの応援を披露できる素晴らしい場だったなと思います。試合結果として最後は負けてしまったんですけど、どの大学よりも応援の本質を感じる経験ができました。勝ってるときは応援も楽しいですけど、負けてる時ほど選手は応援が欲しいと思います。一緒に戦ったから、負けた瞬間は私たちも悔しいと思いましたし、その負けからも“応援をしている意味“というものを神宮で感じられたのかなって思います。

(提供:東洋大学應援指導部)
――鉄紺祭の見どころは
普段は応援指導部としての活動がメインですので、楽器部門のメドレーのステージやチアリーダー部門のチアのステージ、リーダー部門の演舞をそれぞれを見せる機会はあまりなかったので、それぞれのステージを楽しんでいただけるかなって思います。
最後のフィナーレでは応援指導部として、三部が一体になる姿をお楽しみいただけるかと思います。
――第5回ということで、まだ歴史としては浅く、これから歴史を築いていくことになると思います。その中で今回は一つの節目になりそうですが、今回の鉄紺祭への意気込みを教えてください
私たちはコロナ禍を経験して、うまく活動できなかった世代です。皆様の前で演舞を直接お見せできるのが最初で最後になります。一時は廃部の危機でしたが、その危機を乗り越えた新しい応援指導部の姿を、新しい「熱叫応援」をお楽しみいただけたら嬉しいです。

今回のインタビューでは「鉄紺祭」のほかに、夏に行われた「鼎(かなえ)の舞」についてもインタビューを行った。
「鼎の舞」とは
「鼎とは中国最古の王朝である殷の時代から祭器として用いられ、歴代の宋朝における宝器とされた、三本足で二つ手のある底の深い器の事です。この歴史ある貴き鼎のその姿から、東都大学を支える三本の足として、亜細亜大学、駒澤大学、東洋大学の三大学応援団体一同に会し、互いに切磋琢磨し練り上げた演奏と演技の二つの手で繰り広げたこのステージを~かなえのふ~と命名しました」(鼎の舞公式パンフレットより引用)
今年度行われたのは「第十一回 鼎の舞 東都三大学応援の集い」といい、19年ぶりの開催であった。亜細亜大学体育会応援指導部の皆様、駒沢大学応援指導部の皆様、東洋大学応援指導部の皆様が8月19日に亜細亜大学3号館講堂に集合。互いの応援に敬意を払いながら華やかなステージを作り上げ、観客を魅了した。

(提供:東洋大学應援指導部)
――19年ぶりに復活の話をいただいた時の感情は
元々駒大、亜大、東洋大で「鼎」っていう集まりがあるのは知っていました。しかし、「鼎の舞」という大学の枠を超えた演舞祭があることは知らなかったので驚きました。私たちはコロナ世代で上手く活動出来てなかった中で、19年前に終わってしまったものを復活させるという一大イベントに心を躍らせていました。
――複数の応援指導部が揃い、自分たちで作り上げた一大イベントでしたね
応援団フェスタというものにも参加させていただきましたが、応援団フェスタは出場校が多く大規模だったのに対して、鼎の舞は同期・同志で演舞祭を作り上げました。このように0から作り上げるのは楽しかったです。
――3校が揃ったときに感じた東洋大の強みはありますか
スローガン「熱叫」にもあるように声の部分ですね。リーダー部門だけでなくチアリーダー部門や楽器部門も全て同じ熱量で叫ぶことができるので、その部分は負けてないのかなって思います。
――迫力がありながらも、笑いを誘う部分もある。想像とはまるで違った楽しい雰囲気が終始漂っていました。楽しい演舞祭でしたが、終わってみていかがでしたか
ありがとうございます。終わってみて、安心した気持ちが強かったです。19年ぶりの開催ということで、演目だけでなく施設やお金の面を含めて、19年前にどのように始まり、どのように終わっていたのかわかりませんでした。しかし、「鼎」という集まりを大切にしたいと思い、暗中模索の中で動いてやり切れたのはこれ以上にない大学生活の青春だったなって思います。先輩方からも好評で、安心しました。

(提供:東洋大学應援指導部)
――最後の開催が19年前ということでまだ生まれていない部員の方もいる
そうですね。1年生はまだ生まれてないかもしれないです。
――1度止まった歴史を動かす、このことに対してプレッシャーはありませんでしたか
もちろんありました。応援指導部や応援団というものは19年前は今より厳しかったと思います。パンフレットや演目の内容、3校の共演などで、もしかしたらご指摘をいただくかもしれないという考えもありました。各校に伝統がある中で、フィナーレで全校が揃って各校の応援歌の振りを行う演出をしました。伝統のある振りを振らせていただくのは、緊張しますし下手なところをお見せできないので各部門がとても練習を重ねました。
――「鼎の舞」から得られたものは何かありますか
今まで、自分の大学の中でも頑張っている同期がいて、「私も頑張ろう」と思えました。他大学の皆様も華々しい演舞をしていても、彼らも努力や苦悩を積み重ね、その結果が華々しい演舞を生み出しているのだと改めて知ることができました。同じ悩みを持ち、同じように努力を重ねている仲間がいる、仲間が増えたことが良かったかなって思います。
――「鼎の舞」を開催してよかったですか
心の底からやってよかったと言えます。
□開催概要□
第5回 鉄紺祭
日時:12月3日
場所:東洋大学白山キャンパス円了ホール(無料)
時間:開場13:00/開演14:00 閉演予定17:30

聞き手・TEXT・PHOTO=成吉葵